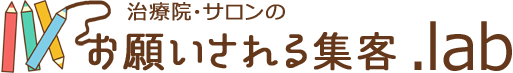この【 短編集つくろう!】 は、文章が苦手な人でも電子書籍をつくることができる eラーニングのプログラムです。
具体的には、
● 長い文章が苦手なひと
● 今までに書いたブログやメルマガの記事を、一冊の本にしたいというひと
● 新しくブログやメルマガを始めて、その記事を電子書籍としてまとめたいひと
に向けた内容になっています。
そして基本的には、ビジネスを持っているひとが、集客の役に立つような電子書籍のつくりかたをお伝えしていきます。
もしあなたが
「ブログ書こうとすると眠くなる」
「メルマガって何書けばいいのか分からない…」
「情報発信しても続かない」
「忙しくって出版なんて無理」
「とにかく文章が面倒くさい!」
とお悩みなら、このプログラムは必ず役に立ちます。
情報発信って必要なのか?
はじめまして。電子書籍つくろう!プログラムを主宰している伊東 歩です。
あなたには、「こんな人と仕事がしたい!」という理想像はありますか?
それは顧客かもしれませんし、いっしょに仕事をするビジネスパートナーかもしれません。
もしそういう理想の人がいるなら、情報発信が必要です。
逆にどんな人でもいいなら、わざわざ時間を使って情報発信するのは無駄。
ひたすら広告やキャンペーンを打っていればいいだけです。
面倒くさい情報発信をわざわざするのは、あなたが仕事をしたい人と出会うためです。
たとえば、わたしは鍼灸師なのですが
● 治療に対して「自己投資」という感覚を持っている
● 人の身体はそれぞれ違うと理解している
● 提案したセルフケアをこつこつ続ける
● 小さな変化を喜べる
● 話が合う
という人の施術がしたい。ですからブログやメルマガで
「その場しのぎの治療は、そろそろやめませんか?」
「万人向けの情報は鵜呑みしないでくださいね」
「セルフケアは自己愛そのものだと思います」
「身体が変わるってすごいことなんです!」
などと伝えるようにしています。
長くつき合える人が集まる
先ほどのような情報を発信していると、自分の考えに共感してくれる人が集まるようになります。
すると当然、長いつき合いができます。
情報発信というのは、いわばコーヒーのドリップ。
自分に合う人をフィルターで選別して、漏斗(ろうと)で集めて囲い込むのですから。

仕事が楽になる
情報発信をしていると、次のような変化が起こります。
● 通ってくれる人を楽に集客できる
● 楽しく仕事ができる
おためし料金のお得感を目当てに来院した人が、通常の価格に戻ったら来なくなるパターン。
よくありますよね?
「いちど施術を受けて、良さを分かってくれたら…」
というコチラの願いは、お得感重視の顧客には響きません。
そこじゃなくて、あなたの思いや人となりを気に入って集まった人は、自然とリピートしてくれます。
経営的に嬉しいのもありますが、なにより、気の合う顧客と深く長く付きあうことができる。
治療業は継続してナンボってところがあるので、症状も改善していく。
すると、仕事をしていてもとにかく「楽しい」と感じることが増えたのです。
情報発信をしていると、このような嬉しい変化があるのですが、弱点もあります。
情報発信の弱点とは
ブログやメルマガ、電子書籍を使ったWeb上の情報発信は、『情報資産』と呼ばれます。
それは、自動的に顧客を集めてくれる媒体だから。
しかも電子書籍なら、amazonが勝手に見込み客を選んで繰り返しアプローチしてくれる。
ただ、弱点もあります。それは、
● 面倒くさい
● 時間がかかる
● 文章が苦手
● 続かない
ということ。
弱点を強みに変える【短編集】という戦略
ファン化しやすい濃い顧客が自動で集まり、仕事が楽しくなる情報発信。
やればいいのは分かっているけれど…
マーケティングや集客のセミナーを受けて「よしっ、やるぞ!」と意気込んだけれど、パソコンの前でフリーズ。
1週間後には、もうブログが滞っている。
そんな人でも情報発信をして、「好きな人」をたくさん集めるには、どうしたらいいのか。
編集の現場で培ったノウハウに加えて、自分自身でも7冊がAmazonランキング1位を獲り、
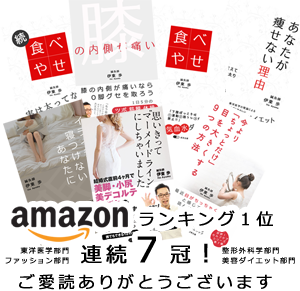
月間60,000PVを集めるブログやメルマガを運営してきた経験を活かして、
- 文章が苦手
- 面倒くさがり
- 長続きしない
人でも電子書籍が出版できるようにできたのが【短編集つくろう! eプログラム】です。
プログラムの冒頭部分「ごあいさつ」を一部抜粋しましたので、ご覧ください。
「面倒くさい」を解消
もしあなたが、すでにメルマガやブログを書いているなら、その記事を集めて短編集がつくれます。
つまり、記事の再利用ですね。
わざわざ新しく短編を書く必要はありません。
そうではなくて、今まで全く情報発信をしていない場合は、ある程度文章を書く必要があります。
ただ、デジタルコンテンツは使い回しできるのが長所。
たとえばブログの記事をいくつか書けば、それをメルマガにも、SNSにも、そして短編集の電子書籍にも利用できるので、少しの作業で多くの発信をすることができるのです。
「時間がかかる」を解消
情報発信をしていると顧客教育できますが、結果が出るまでに時間がかかります。
しかし電子書籍は一冊で顧客教育ができるので、時間短縮ができるのです。
しかもブログやメルマガと違うのは、Amazonという日本最大の書店が味方になってくれるところ。
いくら頑張ってブログを書いても、なかなか人目に触れません。
でも電子書籍なら、Amazonのマーケティング力によって、あなたの本を必要としている人を探して売ってくれるのです。
「文章が苦手」を解消
本を書くと聞いただけで、「無理!」と思うひとも多いです。
話を聞くと、あんなにたくさん書けないというのです。
でも大丈夫。短編集ですから。
気が向いた時にひとつの短編を仕上げて、休憩。それをいくつか集めれば本が完成します。
しかも短編を書く秘訣として、3つのテンプレートを用意してあります。しかも分かりやすい例文つき。
あなたはテンプレートを埋めるだけで、しっかりとした構成の文章ができあがります。
「続かない」を解消
情報発信で集客するなら、ある程度続けることが必要です。
でも電子書籍は続けなくていいんです。
一冊つくっておけば、出版によるブランディング効果もあるし、なによりAmazonが勝手に見込み客を探してくれる。
Amazonは本を売りたいので、膨大な顧客情報の中から、あなたの本にぴったりな顧客に本を紹介します。
しかも商業出版と違って電子書籍は場所を必要としないので、何十年もずっと、あなたの本は最前線に並んだままになるのです。
いま、出版をすすめるのは…
もしあなたが健康・美容のビジネスに携わっているなら、今、出版しておくことをおすすめします。
これから広告の規制が厳しくなり、宣伝できることがかなり限られてきます。
「〇〇という雑誌に掲載されました!」という宣伝すらダメ出しを食らうかもしれません。
でも自分で書いた本なら?
何の問題もありません。
HPでもチラシでも、「私の出版した本です」と紹介するだけで、今の時点ならかなりの差別化になります。
そして広告で書けなくなったことを、本の中で伝えればいいのです。
本当は簡単なのに、「本の出版なんて難しそう」と多くの人が思い込んでいる今のうちに本をつくっておいて、著者としての評価を確立してしまいましょう。
プログラムの内容
大まかにお伝えすると、普段の情報発信に使えるように【ブログ】【メルマガ】【オウンドメディア】それぞれのタイプのテンプレートについて学んでいただきます。
それをベースに短編を書き、編集して、無料のソフトを使って原稿を電子書籍化。
ファイルをAmazonにアップして販売する方法をお伝えします。
基礎編
ごあいさつ
これから短編集をつくりはじめるひとに、短編集の魅力や、「こんな気持ちでつくってください!」という思いを伝えさせていただきます。
執筆編
執筆編では、短編集を構成する短編の書きかたを学んでいただきます。
【 ブログ・タイプ 】
【 オウンドメディア・タイプ 】
【 メルマガ・タイプ 】
という3つの執筆方法は、普段の情報発信にも、短編を書くことにも役立ちます。
● あなたがすでに情報発信をしているなら、この執筆編を参考に記事を磨きましょう。
● これから情報発信をするなら、まずはざっと執筆編を学んでみて、どんな方法が自分に合っているのかを決めてください。そして実際に情報発信をしながら、記事のいくつかを短編にしましょう。
● 情報発信をするつもりはなくて、電子書籍作成のための短編を書きたいひとも、ひと通り執筆編をご覧ください。そして色々なタイプの短編を書いてみてください。
そして短編(記事)がいくつか集まったら、『編集製本編』を参考に短編をまとめて出版するのです。
いずれにしても、短編集の魅力は気軽で自由に本をつくれるところ。
一応書きやすいように全てのタイプのテンプレートをご用意していますが、あなたの好きなように書き進めてください。
あなたに合う執筆方法を3つのタイプからみつけよう
● 書きやすくてクオリティの高い記事がつくれる3タイプ
● 「お役立ち情報型」「親近感型」「問題解決型」
● テンプレートに当てはめて書くだけ
ブログとオウンドメディアの違い
● すでに見込み客と接点があるのかどうかで選ぶ
● 検索してもらいやすいという長所を活かす
● 親近感か信頼感か
● 使い捨てのフロー型と情報資産となるストック型
● 集客のどの段階が足りないのかで文章が変わる
ブログタイプのテンプレートを使いこなす
● 3つのパートから成るシンプルな構成
● 各パートの具体的な書きかた
● ブログ読者が知りたいのは記事内容だけではない
● 2つの具体例を参考に書いてみよう
● 適度に4つめのパートを入れて集客・セールスにつなげる
オウンドメディアタイプの記事で最も重要なこと
● 守らなければならない唯一のルール
● オウンドメディアの読者が求めているものを知る
● 後発組が検索エンジン対策(SEO)で優位に立つキーワード
● 電子書籍の出版で先行者利益を得る
● 特定の分野で第一人者となるためにすること
オウンドメディアタイプのテンプレートを使いこなす
● 論理的な文章で読者から信頼を得る
● 6つのパートは論理的に納得しやすい構成になっている
● 裏付けデータをどうやって書き込むか具体例から学ぶ
● 解決方法の提示は2段階で伝えると分かりやすい
● あなたにしか書けない根拠こそが文章の価値を高める
● 5つ目のパートで疑似体験させたら予約の電話が増えた実例
● 最後のパートでビジネスへの布石を打っておく
メルマガ最大の長所は「ラブレター」
● メルマガの強みを知って読者と信頼関係を築く
● メルマガは古いけれどなぜ今も残っているのか
● あなたが使える全てのメディアと比較
● 「あなたが勧めるなら、そうしよう」と言わせるために意識すること
メルマガで「誰が」「何を」「誰に」つたえるのか
● あなたと読者のメルマガに対する目的は違う
● 無理なく書き続けられるメルマガのテーマ選び
● BtoB と BtoC でテーマを変える
● 真実味のある話を伝えるために文章力は関係ない
● あなたの「人となり」をどのタイミングで伝えるのか
メルマガタイプのテンプレートを使いこなす
● 少ない文章量でもしっかりと情報が伝えられるテンプレート
● 書くのがラクな結論前出し型の構成とは
● 具体例を参考に3つのパートを理解する
● 先を読み進めたくなる書き出しの秘訣
次回が待ち遠しくなるメルマガの書きかた
● ザイオンス効果を発揮するための文章術
● 読者登録をしたひとはメールを開いていない
● メール開封率を上げる2つの方法
● 次のメルマガを読む理由が無い
● メルマガ冒頭で関係性と理解を深める
読者の生活の一部になるメルマガ
● 最低限守らなければならないマナー
● メルマガを送る最適のタイミングとは
● 相手の中にあなたの居場所をつくるコツ
● どのくらいの頻度でセールスを入れる?
● どうやってビジネスにつなげると自然なのか
読みやすいメルマガ3つのコツ
● メルマガ独特の表現の工夫
● 写真・色・太字がなくても分かりやすく書ける
● 短編集にも合っているシンプルな文章
● パッと見で読みたくなくなるメルマガとは
● 遊び心が読みやすさにつながる
編集製本編
編集製本編では、書いた短編を編集して、一冊の本にまとめて、実際にAmazonから発売するまでの手順を学んでいただきます。
自由に書いて集めた短編が、ちょっと工夫するだけで「ぐっ」と本らしくなる秘訣をお伝えします。
ぜひ編集製本編を参考にして、100年後まで残るあなたの分身となる本を完成させましょう。
どんな手順で短編集をつくるのか
● 短編集が完成するまでの流れを理解する
● 手順に沿って作業をすれば出版できる
出版に適した原稿の準備
● 電子書籍の出版に必要なソフトとは
● 電子書籍に最適な ePUB形式について
● 余計な手間を省きファイルの紛失を防ぐためにしておくこと
● 原稿を書き始める前に必ず読んでおく資料
たくさん書けばそれだけ売れる?
● トータルの文字数と短編の数とのバランス
● 短編集の「読みやすさ」という特性を活かす
● いくつかのタイプを組み合わせて満足度の低下を防ぐ
短編の選びかた次第で価値が変わる
● 短編選びの基準
● 技術の進歩を利用してピンポイントのテーマで攻める
● 「その分野の専門家である」というイメージを持たせる
● メイン短編と補足短編の組み合わせを具体例から学ぶ
● 「同じような記事が並んでしまう」という定番の質問に対する答え
選んだ記事を原稿に貼りつける方法
● ブログ・メルマガ・オウンドメディアなどオンライン上で作成した記事を原稿に貼りつける方法
● 貼りつける形式に注意
● 改行とスタイル設定のコツ
短編を並べる3つの法則
● 短編を並べる順番は編集の腕の見せどころ
● 読み放題サービスに対応した並べかたが必要
● マクロからミクロに
● 電子書籍の目次を味方につける
● 短編集の長所「気軽に読める」を活かす
読みやすい文章4つの秘訣
● 縦書きと横書きどちらを選んだらよいのか
● 狙った印象で「です・ます」「である・だ」を統一する
● つい忘れがちな改行のあとにしておくこと
● 国語の授業なら怒られる改行方法
読者を惹き込む見出しのつけ方
● ブログやメルマガにはない「小見出し」をつける3つのコツ
● 書いてある内容をまとめてはいけない理由
● 「見出し = もくじ」 をいつも意識しよう
● 見出しはセールスである
● 小見出しの前後に改行を入れない
短編集は「まえがき」で完成する
● 短編集と一冊丸ごと型書籍の違いとは
● 親切なレストランのメニュー表を目指す
● 選んだ短編によってまえがきを変えよう
● まえがきで「あなた」を売り込む方法
● 読者の頭のなかでは何が繰り返されているのか
短編の最後に締めが必要な理由
● 読者は読んではいるけれど理解していない
● 文章の要点とセールスを分けて考える
● 短編集でセールス感が出過ぎない工夫
● 具体例から学ぶ「まとめ」のつくりかた
● 全ての短編を同じに扱わない
あとがき・奥付に書くべきこと
● 精読率が落ちやすい短編集をどうやってビジネスにつなげるか
● 短編集のあとがきにはファンが集まる
● 見込み客の行動をコントロールしよう
つい本が読みたくなる内容紹介
● 販売ページに載る内容紹介には何を書けばいいのか
● 短編集は3つのポイントをおさえれば大丈夫
● 「短編集 = 気軽」というイメージを利用しよう
● いちばん簡単な内容紹介のつくりかた
あなたを高く売るプロフィールの書きかた
● プロフィールは顧客から選ばれるための理由を書けばいい
● 履歴書にならないためのちょっとした工夫
● 「専門分野なら任せてください」と表現するプロフィールとは
● 嫌われずにあなたの人間味を染み込ませるためにすること
● 安い人間だと思われないための注意点
内容より大事なタイトルのつけ方
● タイトルを変えただけで売り上げが変わる
● タイトルとサブタイトルの役割分担
● 内容とタイトルは関係なくていい
● 真面目なひとがハマりがちな罠
● まずはこのパターンからはじめよう
表紙で印象を脳に刻み込む
● 表紙をつくるための方法は3つ
● 売れている表紙を真似してみよう
● デザインの専門家に丸投げしてはダメな理由
● おすすめの外注サービス
● 模様にならない文字の使いかた
いくらで売ればいいのか
● 何を基準に価格を決めればいいのか
● 短編集を集客ツールにする方法
● どこでお金を稼ぐのかを決めよう
● Amazonランキング1位を狙う価格戦略
● 濃いファンを育てるための価格とは
出版までの流れ
● 短編集の原稿を ePUBファイルに変換してAmazonで販売するまでの流れ
● 4つの段階に分けて進める
原稿を ePUBに変換
● 短編集にするまえにファイル形式を確認しよう
● 便利な無料変換ソフトの使い方
● 作成される2つのファイルのどちらを選ぶのか
原稿をプレビューアーでチェック
● 短編集をAmazon登録する前に電子書籍としての修正をしておこう
● Amazonが提供する無料チェック用ソフトの使い方
● チェックしておく6つのポイント
● 細かい部分は登録時に確認しよう
KDPへのサインイン
● AmazonアカウントとKDPアカウントは別に登録が必要
● すべての手順を画像で確認しながら進む
● 印税が振り込まれる銀行口座を決めておく
原稿をKDPに登録して出版
● 出版前に最終チェックができる
● 登録時のカテゴリー選びは思い通りにいかなくていい
● これまでの講義で準備をした項目をそのまま記入するだけ
出版後にジャンルの修正する方法
● あなたの短編集をランキング1位にするために
● 「穴場ジャンル」を発見するコツ
● 選べるジャンルの表示方法
● 修正依頼に必要な4つの項目
● KDPに送る修正依頼メールの具体例
5つの特典講義
その1:「上手い!」と言われるタイトルの秘訣
① 思わず開いてしまうメルマガタイトルのつけかた
● タイトルよりも開封率に影響のある要素とは
● メルマガを開かせるタイトル5つのコツ
● 刺激に慣れた読者に「現実味」を伝える
● 脳を起こすキーワードを入れよう
● 上手いタイトルの何を盗むのか
② アクセスの集まるオウンドメディアのタイトルのつけかた
● 検索エンジンにとってタイトルとはどんな役割なのか
● 「ひねり」「インパクト」は必要ない
● 具体例からタイトルのつけかたを学ぼう
● 進化する検索エンジン
● 読者がクリックするための5つのコツ
その2:【目的別】短編集のつくりかた
『後世の人に自分の経験や知識を残したい』
『本にまとめることで人生の棚卸がしたい』
『とにかく出版自体を楽しみたい。本が出してみたい』
という3つの目的について、それぞれの短編集をつくるときのコツをお伝えします。
① 後世の人に何か残したい
● 商業出版は書店から消えるが電子書籍は100年後も残る
● なぜ「背景」を伝えなければならないか
● 源氏物語を参考に
● 独りよがりの文章にならないために
● あなたの生きてきた証を形にする
② 出版を通じて人生の棚卸しをしたい
● 次のステップに進むために今までの人生を振り返って一冊の本に整理する
● どうやって書き進めたらいいのか
● 何をピックアップするか
● 「あとがき」に全てが凝縮される
● 言葉にすることで分かることがある
③ とにかく出版してみたい!
● 日本最大の書店に自分の本が並ぶ!
● バラバラな短編を「まえがき」を使って統一感を出す方法
● ちょっとだけ値段に気をつけて
● 表紙にはこだわろう
その3:使える! まえがき3つのパターン
短編集にとって重要な「まえがき」の書きかたについて、3つの代表的なパターンを学んでいただきます。
● 【並列パターン】お役立ち情報型の短編集向け
● 【論理構造パターン】問題解決型の短編集向け
● 【ばらばらパターン】自由な寄せ集め型の短編集向け
● それぞれの具体例
その4:メルマガ登録を後押しする特典 e-book作成術
プッシュ型のメルマガは、現在も最強のビジネスツールです。
そして電子書籍とメルマガのコンビは、簡単だけど集客に効果的だということは、短編集つくろう!の本講義でお伝えしました。
この特典講義では、メルマガの登録率を上げるための、プレゼント用の電子書籍のつくりかたをお伝えします。
● 「持っておいてもいいな」という絶妙のテーマ選びのコツ
● 凝った構成は必要ない
● 特典用電子書籍の文字数と表紙
● つくった特典を簡単に読んでもらう方法
● どのタイミングで読者に渡せばいいのか
その5:短編集を集客とビジネスにつなげる方法
この講義は、『組み立て式 電子書籍つくろう!』というプログラムのステップ5としてお伝えしていたものです。
短編集を完成させた方に、出版して終わりではなく、そこから集客やビジネスにつなげて欲しいという思いから特典とさせていただきました。
あなたの知識や経験を一冊の本にまとめるのは、困っている誰かの役に立つということ。
ぜひあなたのつくった短編集をきっかけに、人の輪を広げていただければ嬉しいです。
ビジネスにつなげる2つの方法
● 電子書籍の出版をビジネスにつなげるにはどうすればいいのか
● 「即効性のあるもの」と「長期で戦略的に進めるもの」の2通りの方法がある
電子書籍をブランディングに利用する
● 出版したその日から実践できることがある
● 出版して得られる最大の評価とは
● どんなメディアが使えるのか
● 休眠客を呼び戻すキャンペーンに利用する方法
● 「ランキング1位」と「表紙」で攻める
Amazon著者ページで強力なブランディング
● 著者ページという「公的なもの」を上手く利用する
● Amazon著者ページは自分でつくる必要がある
● 顧客があなたの名前を検索したとき何が起こるのか
少ない資本の個人が効率的に集客する方法
● 広告費 → 集客 → 広告費 のループから抜ける
● 見つけてもらいやすいストック型コンテンツを活用する
● 使い捨て情報を減らし情報資産を増やす
● 価格の安さやインパクトに頼らず「顧客を育てる」仕組みをつくる
二段階でクロスメディア戦略を使いこなす
● 問題解決から信頼感へ段階的につなげるために必要なこと
● 電子書籍を使って潜在顧客と出会うきっかけを増やす
● せっかくの出会いを無駄にしないプッシュ型メディアの強さ
● 2つのメディアがあれば簡単にできてしまう
デジタルコンテンツの長所を活かす方法
● あなたは著作権を持っているという強味
● 全ての発信に同じ労力をかけてはいけない
● なぜ多くの発信を同時にできるのか
● 短編集はデジタルコンテンツの再利用で簡単につくれる
どこで稼ぐのかキャッシュポイントの決め方
● 「つい儲けたくなる」という欲が裏目に出る
● 導線とゴールを常に意識する
● キャンペーン客とファン候補に等しく時間を使ってはいけない
● マーケティングファネルを参考に顧客への最適な行動を選ぶ
「無料」に注力してファン・リピーターを増やす
● 「楽して儲ける」の本当の意味
● ファンを育てる一本の線をつなぐ
● ゼロ → イチ ができたら喜んでいい
● なぜ無料の情報発信にエネルギーを注ぐ必要があるのか
ひとに教えることで大きな収入を得る
● 顧客を変えれば収入が変わる
● 開業1年目でも教えられることがある
● 「私なんか…」から「私だからこそ!」へ
● 電子書籍は最強のテキスト
● 身体が動かなくなってもできる仕事を持っておく
推薦の言葉をいただいています

出口 汪 (でぐち ひろし)氏
出版社『水王舎』会長 東進ハイスクールの現代文・小論文講師 広島女学院大学客員教授
受験生で知らない人はいないというくらいのカリスマ現代文講師
偏差値が30以上上がったり、学校が変革されたりと、「世界一受けたい授業」などの数多くのテレビ出演や、「読売新聞」「アエラ」「週刊現代」「プレジデントファミリー」などの雑誌で大きく報道され話題となる。
現在、様々な電子書籍に関する教材が巷に溢れかえっているが、この『組み立て式 電子書籍つくろう!』『短編集つくろう!』のような、論理を活用した教材が登場するのは画期的である。
それにより、誰でもわかりやすく、多くの人に伝わる本を書くことが可能になった。
このようなわかりやすい電子書籍づくりの教材が完成したのは、伊東さんの誠実な人柄と、豊富な経験の賜物であろう。

長倉 顕太(ながくら けんた) 氏
コンテンツマーケター・出版プロデューサー。元フォレスト出版取締役編集長兼マーケティング部長。編集者歴10年で書籍売上1000万部超。
コンスタントに毎年100万部以上売ってきた実績は、業界で圧倒的な数字。
主な担当書籍に
シリーズ70万部『怒らない技術』(嶋津良智著)
シリーズ70万部『「心のブレーキ」の外し方』
シリーズ70万部『なぜ、占い師は信用されるのか?』
(ともに石井裕之著)
シリーズ50万部『英語は逆から学べ!』(苫米地英人著)
シリーズ70万部『なぜ、社長のベンツは4ドアなのか?』(小堺桂悦郎著)
『略奪大国』(ジャームス・スキナー著)など。
伊東さんは、素直に学び、それを実行し、成果を出し、報告することができる人です。
私は職業柄多くの成功者に会ってきておりますが、素直、実行、成果、報告ができる人だけが成功するのが世の常なのです。でも、多くの人がこれができない。
じゃあ、できる人とできない人の差はなんなのか?
ずばり、私は人生に対するセンスだと思うんです。成功している人は人生に対するセンスが良いから成功するわけです。当然ですが、センスが良い人から学ばないと成果なんか出ません。
だから、私は伊東さんのプログラムを推薦します。誰から学ぶかを間違って欲しくないからです。
ご相談ください
もしあなたが、「電子書籍づくりに興味がある」と思ったら、まずはご相談ください。
どんな目的で、どんな内容の本がつくりたいのかを聞かせていただければ、アドバイスをさせていただきます。
決して「電子書籍を出版したほうがいいですよ!」と押し付けるようなことはありませんので、ご安心ください。